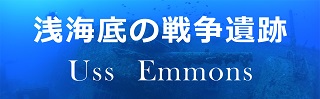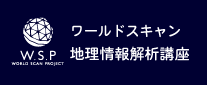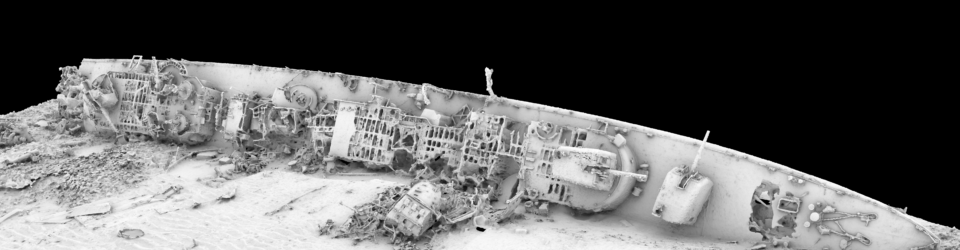私の研究室では,サンゴ礁地形の形成過程とそれに関わる第四紀の環境変遷,熱帯島嶼域における防災・人と自然との共生をテーマとした研究を行っています。これには,マルチビーム測深を用いた高精度海底地形図の作成や,水中ボーリング機などを使っての試料採取,電子顕微鏡などの装置を用いた試料分析など様々な研究方法を用いています。また太平洋・インド洋の環礁国では,サンゴ礁の形成に関する研究とともに,環礁洲島の地形と津波災害および温暖化など地球環境問題の影響に関する研究を進めています。詳しくは研究内容の紹介ページをご覧ください。
菅 浩伸 九州大学大学院 主幹教授
地球社会統合科学府(教育組織) 比較社会文化研究院 環境変動部門 基層構造講座(研究組織) 浅海底フロンティア研究センター センター長専門:自然地理学,サンゴ礁地形学,海底地形学 主な調査地域:琉球列島,オーストラリア・グレートバリアリーフ,太平洋諸島,インド洋モルディブ諸島
自己紹介と主な研究実績は、こちら